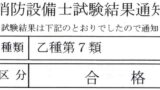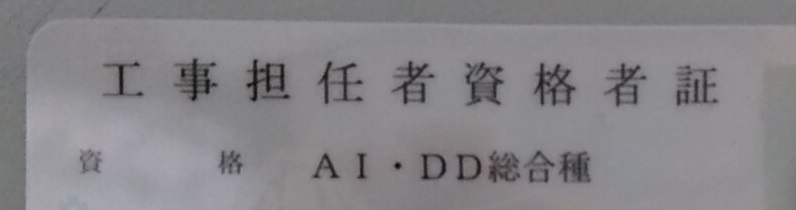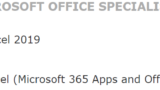どんな資格?
一般住宅や小規模な建物の電気設備工事(600V以下)を実施するための国家資格です。
また資格を持っていると、事業用電気工作物を設置する事業者等に義務づけられている電気主任技術者の選任を受けることができます。
最近は、電気技術者が不足しているので、需要は結構ありそうです。
自宅の電気配線なんかもできますので、最近はDIY目的でとる人もいるようですね。
きっかけ
昨年、消防設備士乙6,乙7を取得しました。
乙7を申し込んだ後に実は電気工事士を持っていると、実技が免除になることを知りました。
次は、4類の取得を考えていたのですが、ここでも電気工事士を持っていると一部科目免除があることがわかりました。
…消防設備の4類に挑戦する前に電気工事士を取った方が効率いいのかも⁉
と思い、先に電気工事士を取ることにしました。
試験について
試験機関:一般社団法人 電気技術者試験センター
試験日:学科上期…5月の下旬の日曜日(CBT方式は、4月の半ば~5月の初め)、下期…10月下旬の日曜日(CBTは、9月半ば~10月の初め)、実技:上期…7月半ばの土曜日ot日曜日
申込期間:上期…3月半ば~4月初め、下期…8月半ば~9月の初め)
受験料:インターネット申込み 9,300円、郵送申込み 9,600円(いずれも非課税)…ですが、事務手数料で297円プラスされます
合格率:筆記…約60%、技能…約70%
受験資格:なし(年齢・学歴・経験不問で誰でも受験可能)
免除制度:筆記免除制度あり…前回合格者、電気系学科卒業者、電気主任技術者などは筆記試験が免除されます
勉強時間:約50時間(2ヶ月程度)
学科学習費用:5,000円程度=入門書…2,000円、テキスト…2,000円、問題集…1,000円
実技学習費用:テキスト…2000円程度、練習キット…1回10,000円程度、工具…15,000円程度、実技講習40,000円程度
申込方法:HPから申し込み
サイトのアドレス:https://www.shiken.or.jp/
勉強方法
電気関係は、工事担任者を持っていますが、これはソフト寄り。
入門書
がっつり電気系は初めてになります。
ので、まずは優しい入門書から入りました。
読んだのは、「すい~っと合格コミック マンガで〝そこそこ〟わかる 第2種電気工事士 学科+技能入門」です。
タイトルに”そこそこわかる”とあるように、そこそこわかりまます。
電気系が初めての方や、とりあえず概要を掴みたい人にはお勧めです。
(電気のことがそこそこわかってる方にはちょっと物足りないと思います。)
テキスト
さて次はいよいよテキスト読みです。
いくつか見比べましたが、自分にとってわかりやすかったので、「ぜんぶ絵で見て覚える 第2種電気工事士 学科試験 すい~っと合格」にしました。
このテキストは見やすいだけではなくて、他のテキストより1サイズ小さいB5なので、重さ的にもサイズ的にも持ち運びに便利です。
(電気工事士のテキストって、なぜかA4サイズが多いんですよね…。)
後半は、180問の厳選問題もあります。
この180問は、最低限覚えておきたいですね・
ということで、試験までに8周しました。
また、巻末にはミシン目で取り外し可能な”丸暗記ノート”が付いてきますので、試験直前の見直しにも大いに役立ちます。
さらに、オーム社のオンライン授業の基礎編が無料で見れたり、ブックライブで電子書籍が見れたり、暗記カードやCBTの模試が受けれたり特典があります。
そう、ここで、オーム社のオンラインスクールがあることが分かりました。
早速無料編を見てみましたが、並列の合成抵抗は何で逆数の足し算になるのか?を知ることができました。
もちろんオームの法則は知っていましたが、並列の合成抵抗の理屈までは知らなかったので、衝撃を受けました。
これは、見る価値があると思い、早速オンラインスクールに入会しました。
オーム社オンラインスクール
費用は、5,500円です。
購入当日 ~ 購入6月後の半年間繰り返し見ることができるWeb動画なので、結構リーズナブルだと思います。
内容は、”第2種電気工事士 学科試験すい~っと合格”テキストに沿っての解説になります。
ので、テキストをただ読むだけでは頭に入らない方は、これを見ながら学習するのも手です。
いつものごとく、倍速でまずはさら~っと通し、問題集を何週かしたらまた復習で動画を見ましたね。
1回目は、よくわからないところも、問題集をといてから見るとわかるところもでてきました。
問題集
基礎固めができたら、早速問題を解いていきます。
使用したのは、この「【すい~っと合格 赤のハンディ】ぜんぶ解くべし! 第2種電気工事士 学科過去問」です。
左ページに問題、右ページに解説が載っていてとても見やすいです。
巻末には重要ポイントもまとめがありますし、さらにはB6サイズなので、持ち運びもしやすくとても好みの問題集です。
基本的には、ここに書いてあるやり方です。
1周目はさらーっと解いて、実力確認。
2週目は、できなかったところに赤線。
3週目は、できなかったところに青線。
(ここらへんで、できなかった問題を、ワードにまとめていき、試験直前に自分の苦手分野の見直しができるようにしておく。)
4週目は、できなかったところに緑線
5週目は、できなかったところに黄色線
…と全部で10週しました。
ここまでくると、問題と答えを暗記していますので、どんな問題が出ても対応できます。
インピーダンスや三相3線式については、ちょっとつまづきましたが、ここはYouTubeで解説動画を見て学習しました。
今は、無料で講義が受けられるので、いい時代になりましたね。
一番お世話になったのは、ここの「ガミデンキちゃんねる」です。
写真鑑別・図記号
写真鑑別と図記号は、丸暗記するしかないです。
ので、よく間違えるものをリスト化し、昼休みに復習してました。
計算問題は得点源
計算問題はパターン化しているので、パターンを覚えれば得点源になります。
インピーダンスと三相3線式の計算が一苦労しましたが、ここは先ほど紹介したYouTube「ガミデンキちゃんねる」で学習。
図で覚えると、理解しやすいですよ。
複線図は苦労
学科で一番苦労したのは、複線図になります。
最初は全然わかりませんでした。
が、ジェイメディアネットの「準備万端シリーズ」の実技講習動画での呪文を覚え、乗り切りました。
「白コンブ」、「黒コンスイ」、「スイッチブ」です。
詳細は、”実技編”で書きたいと思いますが、学科の勉強中に実技の演習セットも揃えていました。
付属していた動画も複線図を描く参考になると思って既に見ていたのですが、そこで紹介されていたのが、この呪文です。
複線図の白の線はコンセントと負荷、黒線はコンセントとスイッチ、残りはスイッチと負荷に繋げる。
という意味です。
最初の頃はこの呪文だけでは流石にのりきれませんでしたが、過去問演習を何度も繰り返すうちに描けるようになりました。
この呪文は、実技試験でも大いに役立ちました。
複線図の過去問演習は必ず毎日数問づつといて、手で覚えるようにしましたね。
でも、結局何度も演習しても解けない問題はでてきました。
ので、難しい問題は捨てることにしましたw
Wordにまとめた不得意ポイント
試験前に見直してた、不得意ポイントを一部紹介します。
漏電遮断器の感度区分
| 感度 | 定格感度電流 | 作動時間 |
| 高感度形 | 30mA以下 | 0.1秒以下 |
| 中感度形 | 30mA超~1,000mA以下 | |
| 低感度形 | 1,000mA超 |
コンセントの図記号
| 記号 | 読み | 意味 |
| E | アース | 接地極付 |
| ET | アースターミナル | 接地端子付 |
| T | ツイスト | 引掛形 |
| EL | アース・リーケッジ | 漏電遮断器付 |
| LK | ロッキング | 抜け止め形 |
| WP | ウォーター・プルーフ | 防雨形 |
| EX | – | 防爆形 |
| H | – | 医用 |
絶縁電線の種類と記号
| 記号 | 読み | 名称と構造 | 用途 | 許容温度 |
| IV | インドア・ビニル | 600Vビニル絶縁線 | 屋内配線用 | 60℃ |
| HIV | ヒートレジスタント・インドア・ビニル | 600V二種ビニル絶縁電線 | 屋内配線用 | 75℃ |
| EM-IE | エコ・マテリアル・インドア・ポリエチレン | 600Vポリエチレン絶縁電線 | 屋内配線用 | 75℃ |
| RB | ラバー・コットン・ブレイデット | 600Vゴム絶縁電線 | 屋内配線用 | 75℃ |
| DV | ドロップワイヤ・ビニル | 引込用ビニル絶縁電線 | 屋外引込用 | – |
| OW | アウトドア・ウェザーブル | 屋外用ビニル絶縁電線 | 屋外配線用 (架空配線用) | – |
電線・ケーブルの最高許容温度
| 種類 | 許容温度 | |
| IV、VVF、VVR | ビニル | 60℃ |
| EM-EEF | ポリエチレン | 75℃ |
| CV | 架橋ポリエチレン | 90℃ |
| MI | 250℃(連続使用温度) | |
ボックス
| ボックス | 用途 |
| プルボックス | 多数の金属管が集合する場所等で、電線の引き入れを容易にするために使用 |
| アウトレットボックス | 金属管工事等、電線工事で管が屈曲する場所や電線の接続、引き出し部分などに使用 |
ケーブルの種類と記号
| 記号 | 読み | 名称と構造 | 用途 | 許容温度 |
| VVF(平形) VVR(丸形) | ビニルインシュレーテッド・ビニルシース・フラット(ラウンド) | 600Vビニル絶縁ビニル外装ケーブル | 屋内や屋外 | 60℃ |
| EM-EEF(平形) EM-EE(丸形) | エコ・マテリアル | 600Vポリエチレン絶縁 耐燃焼性ポリエチレン外装ケーブル平形 | 屋内や屋外 | 75℃ |
| CV EM-CE | クロスリンクド・ポリエチレン・ビニル | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニル外装ケーブル | 屋内、 屋外用 | 90℃ |
| MI | ミネラル・インシュレーテッド | 無機絶縁ケーブル | 高温場所用 | コンクリート内250℃ |
| CT | キャブタイヤ | キャブタイヤケーブル | 移動用電線 | |
| VCT | ビニル・キャブタイヤ | ビニル・キャブタイヤケーブル | 主に 移動用電線 |
管類の種類と太さを表す記号
| 種類 | 記号 | 表綺麗 |
| 薄鋼電線管 | なし | (19)奇数値 |
| 厚鋼電線 | なし | (16)偶数値 |
| ねじなし電線管 | E | (E19)奇数値 |
| 2種金属製可とう電線管 | F2 | (F2 17) |
| 硬質ポリ塩化ビニル電線管 | VE | (VE16) |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管 | HIVE | (HIVE16) |
| 波付硬質合成樹脂 (地中電線路用保護管) | FEP (フレキシブル・エレクトリック・パイプ) | (FEP30) |
絶縁電線の許容電流
| 単線 | より線 | ||
| 太さ | 許容電流値 | 断面積 | 許容電流値 |
| 1.6㎜ | 27A | 2㎟ | 27A |
| 2.0㎜ | 35A | 3.5㎟ | 37A |
| 2.6㎜ | 48A | 5.5㎟ | 49A |
| 3.2㎜ | 62A | 8㎟ | 61A |
ヒューズの溶断時間(定格電流の1.1倍の電流では、溶断しないこと)
| 定格電流 | 溶断時間 | |
| 定格電流の1.6倍の電流 | 定格電流の2倍の電流 | |
| 30A以下 | 60分以内 | 2分以内 |
| 30A超え60A以下 | 60分以内 | 4分以内 |
配線用遮断器の遮断時間(定格電流の1倍の電流では、溶断しないこと)
| 定格電流 | 遮断時間 | |
| 定格電流の1.25倍の電流 | 定格電流の2倍の電流 | |
| 30A以下 | 60分以内 | 2分以内 |
| 30A超え60A以下 | 60分以内 | 4分以内 |
過電流遮断器の種類と容量によって定まる分岐回路の概要
| 配線用遮断器の定格電流 | 電線の最小太さ(軟銅線) | コンセントの定格電流 |
| 20A | 1.6㎜ | 15A、20A |
| 30A | 2.6㎜(5.5㎟) | 20A、30A |
| 40A | 3.2㎜(8㎟) | – |
施工場所と可能な工事の種類
| 工事の種類 | 露出(展開した)場所と 点検できる隠ぺい場所 | 点検できない 隠ぺい場所 | ||
| 乾燥 | 湿気、水気 | 乾燥 | 湿気、水気 | |
| ケーブル工事、金属管工事 合成樹脂管工事(CD管除く) 2種金属可とう電線管工事 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| がいし引き工事 | ◎ | ◎ | × | × |
| 金属ダクト工事 | ◎ | × | × | × |
| 1種金属可とう電線管工事 | ◎※1 | × | × | × |
| 金属線ぴ工事、 ライティングダクト工事 | 〇※2 | × | × | × |
| 平形保護層工事 | 〇※2,3 | |||
電気設備技術基準による低圧用機器の接地抵抗値
| 接地工事 | 使用電圧 | 設置抵抗値 | 接地線の太さ | |
| C種 | 300V超 | 10Ω以下 | 0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置があれば500Ω以下 | 直径1.6㎜以上 (軟銅線) |
| D種 | 300V以下 | 100Ω以下 | ||
電気設備技術基準による低圧用機器の絶縁抵抗値
| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 | |
| 300V以下 | 対地電圧150V以下 | 0.1MΩ以上 |
| その他の場合 | 0.2MΩ以上 | |
| 300V超え | 0.4MΩ以上 | |
リングスリーブ圧着マークの覚え方
| 1.6㎜ | & | 2.0㎜ | サイズ | 圧着マーク | 点 |
| 2本 | + | 0本 | 小 | 〇 | 2 |
| 3~4本 | 0本 | 小 | 小 | 4 | |
| 1~2本 | 1本 | ||||
| 0本 | 2本 | ||||
| 1~3本 | 2本 | 中 | 中 | 5 | |
| 3~5本 | 1本 | ||||
| 1本 | 3本 |
小規模発電設備(600V以下、合計出力50kW未満)
※発電設備を複数施設する場合、その合計出力は、50kW未満
| 設備の種類 | 出力 | 電気工作物の区分 | |
| 電気事業法 | 電気工事士法 | ||
| 風力発電設備 | 20kW未満 | 小規模事業用電気工作物 | 一般用電気工作物等 |
| 太陽電池発電設備 | 10kW以上、50kW未満 | ||
| 太陽電池発電設備 | 10 kW未満 | 一般用電気工作物 | |
| 水力発電設備 (ダムは除く) | 20kW未満 | ||
| 内燃力発電設備 | 10 kW未満 | ||
| 燃料電池発電設備 | |||
| 燃料電池自動車 | |||
| スターリングエンジン発電 | |||
高周波点灯方式(インバータ方式)の特徴(グロースタータ方式と比較して)
| 長所 | 短所 |
| ちらつきが少ない | 電波ノイズが発生する |
| 効率が良い | 高調波が発生する |
| ジーッとういう音がしない | |
| 50Hz/60Hz両方で使える | |
| 小型軽量 |
白熱電灯とLEDの比較
| 蛍光灯 | LED |
| 力率が悪い | 力率が悪い |
| 雑音(電磁雑音)が大きい | 寿命が長い |
| 寿命が長い | 発行効率が高い |
| 発行効率が高い | 価格が高い |
試験は、会場でマークシート or CBT方式
CBT方式にすると、MOSの時みたいにPCでの受験となります。
自分の好きな日にちを受験日に出来ますし、合否がその場でわかります。
が、受験日がマークシートよりも早めな時期になってしまいます。
学科の勉強期間が短くなってしまいますが、合格がわかれば、実技試験に向けての練習期間が長く取れます。
どちらを取るかですが、学科を確実に合格するために普通のマークシート試験を受けることにしました。
学科が一度通れば、翌年も学科は免除で実技試験をうけられるのでね。
試験当日
会場は、地元の大学でした。
集まっている人たちは、老若男女問わずといったところ。
高校生が多かったかな。
恐らく、工業高校の生徒たちでしょう。
実は、会場が開場されるまで入口近くで待っていたのですが、受験票を落としました。
っら、近くの高校生が落としたことを教えてくれました。
感謝です!
さてさて、会場は、それなりの広さの部屋でした。
大学特有?の長机でしたね。
問題用紙でかっ⁉
時間が近くなると、問題用紙、解答用紙が配られますが、問題用紙がB4サイズと大きかった。
いつもは大体A4サイズが相場でしたので、ちょっとびっくり。
ホッチキスで留められてはいないので、一枚一枚外せます。
ので、後半の問題の複線図を描くときは外して、余白に複線図を描きました。
思ったよりスラスラ…?
結構サクサク進められました。
が、数問アレ?ってなってしまいました。
得意のはずの計算問題につまづいてしまいました。
あと、初めて見る問題が数問あったので、それにやられました。
1時間経過すると、退出できるのですが、見直しに時間がかかってしまい、結局最後までいました。
殆どの方が退出してましたね。
結果
自己採点では、4問間違えていたので、92点ですね。
点数的には余裕だったのですが、よく読めば解ける問題に引っかかったり凡ミスがあったりと、ちょっと反省。
まぁ、受かったのでいいのですけどね。
合否は合格通知が来る前に、サイトで確認できます。
合否の発表があってから1週間くらいしたら、合格通知が来たかな?
(なんでこんなに遅いんだろう…。)
学科が受かったら次は、技能試験に向けて実技練習です。